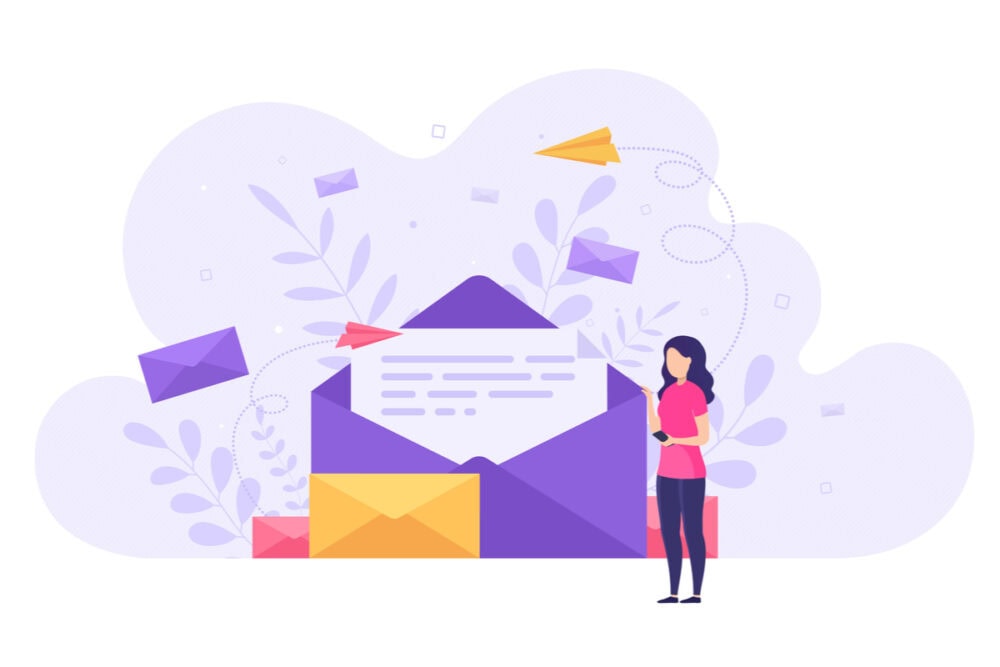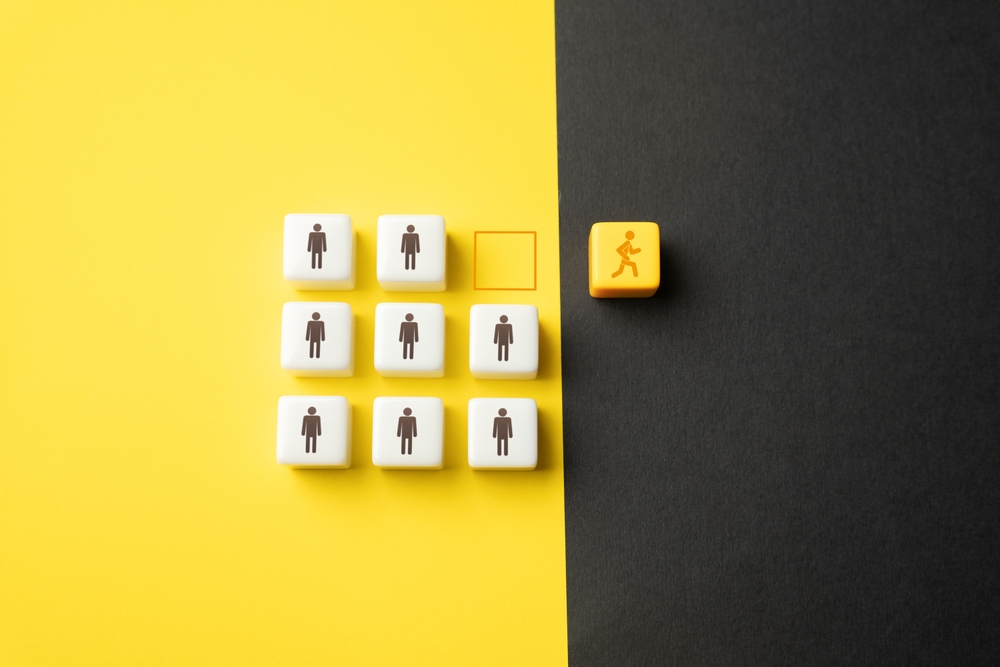
企業の成長を左右する要素の一つに「離職率」があります。離職率が高いと、採用コストや教育コストが増大するだけでなく、組織の安定性や企業イメージにも悪影響を及ぼしかねません。一方、業界平均や企業規模別の平均値を把握し、適切な対策を講じれば、社員が定着しやすい環境を整えられます。本記事では、離職率の定義や計算方法、日本の離職率の推移、業種別・企業規模別の比較データ、さらに離職率が高い企業の課題や改善のヒントを詳しく解説します。
目次
離職率の平均値とは
離職率とは、一定期間内に在籍していた社員のうち、どれほどの割合が退職したかを示す指標です。一般的には以下の計算式で求められます。
離職率(%)=(退職者数 ÷ 期初在籍者数)× 100
たとえば、期初に100名の社員が在籍し、期間中に5名が退職した場合、離職率は5%となります。この指標を用いることで、企業の定着度や人材流動性を客観的に把握できます。
ただし、計算期間や分母・分子に含める対象者の定義(新卒入社を含むか否か等)は企業や機関によって若干差があるため、数値を比較する際には条件を確認することが重要です。
日本の離職率推移
日本における離職率の平均値は、おおむね10%前後と言われていますが、景気や社会情勢、雇用形態の変化によって推移は変動します。
たとえば、以下のような影響要因が挙げられます。
- 経済状況の影響
好景気のときは新規採用が活発になり、人材流動も活性化しやすくなるため、離職率がやや上昇傾向になるケースがあります。一方、不景気のときは転職先が少なくなり、離職率が低下することも考えられます。 - 雇用環境の変化
契約社員や派遣社員など、正規雇用以外の働き方が増えると、企業ごとの離職率が高く見える場合があります。また、リモートワークや副業解禁など、働き方の柔軟性が高まることで、今より働きやすい雇用環境を求め人材の流動性も増加する場合があります。
- 人材の流動性の高まり
若年層を中心に、「自分のスキルを磨きたい」「キャリアアップしたい」という理由で転職を繰り返す人も増えているため、離職率は一部で上昇する可能性があります。ただし、一社で長期的に働き続ける社員ももちろんおり、業界や企業規模でバラつきが大きいのも実情です。
世界平均との比較
世界的に見ても、日本の離職率は比較的低い部類に入ると言われています。欧米の企業では人材の移動が盛んで、企業間での転職が当たり前なカルチャーが根付いているため、10〜15%を上回る離職率が珍しくない国もあります。一方、日本は終身雇用制の文化が長く続き、総じて保守的な雇用慣行が定着していたことから、低めの離職率を維持してきました。しかし、近年は若い世代を中心に転職への抵抗感が薄れ、離職率が高まる傾向も指摘されています。
離職率推移の例
高度経済成長期(1950年代後半〜1973年頃):離職率 約5%前後
- 背景:高度経済成長期には、企業が終身雇用や年功序列を重視し、長期安定雇用が主流でした。労働市場は売り手市場であり、労働者の離職率は低水準で推移していました。
バブル期(1986年〜1991年):離職率 約7〜8%
- 背景:バブル経済期には、好景気により企業の求人が活発化し、転職市場も拡大しました。これにより、離職率は上昇傾向を示しました。
リーマンショック後(2008年以降):離職率 約5〜6%
- 背景:2008年のリーマンショックにより、雇用環境が悪化し、労働者は安定志向を強めました。これにより、離職率は再び低下しました。
近年(令和時代):離職率 約10%近くまで上昇する業界も存在
- 背景:近年では、働き方の多様化や人手不足の影響により、特定の業界で離職率が上昇しています。例えば、介護・福祉業界では、労働条件の厳しさから離職率が高い傾向にあります。
以上のように、日本全体の離職率は一律ではなく、業界・企業規模・経済状況によって大きく異なる点を把握しておきましょう。
出典:
・厚生労働省「令和6年版 労働経済の分析」ホーム|厚生労働省
・内閣府「労働力の確保・質の向上に向けた課題」内閣府ホームページ+1東京大学社会科学研究所+1
・東京大学社会科学研究所「就職氷河期とその前後の世代について」東京大学社会科学研究所
離職率の平均値と業種別比較
業種によっては、人材の流動性が高いものと比較的安定しているものがあります。ここでは、業種別の離職率平均値を表で示すとともに、高低それぞれの業界の特徴を解説します。
業種別 離職率平均値(令和5年)
| 業種 | 離職率(%) | コメント |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 26.6% | 接客業務やシフト制勤務が多く、労働時間が不規則で体力的・精神的な負担が大きい。若年層の比率が高く、転職も活発。 |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 28.1% | イベントやサービス提供のピーク時に労働が集中しやすく、業務負荷が高い。非正規雇用の割合が高く、定着率が低い傾向。 |
| 小売業・卸売業 | 14.1% | 長時間労働や休日出勤が多く、労働条件が厳しいことが離職の要因。大手チェーンでは研修制度や福利厚生の充実により、定着率が改善傾向。 |
| 医療・福祉 | 14.6% | シフト勤務や利用者とのコミュニケーション負担があり、人手不足で業務過多になりがち。特に介護職では離職率が高い。 |
| 情報通信業(IT・ソフトウェア) | 12.8% | スキルアップやキャリアチェンジを目的とした転職が活発。一方、リモートワーク導入で定着率が上昇する企業も増えている。 |
| 製造業 | 9.7% | 工場勤務やライン作業の場合、単調な作業が苦手な人は離職しがち。しかし大企業の工場は待遇面が安定しているため、離職率は低めに推移することが多い。 |
| 金融業・保険業 | 10.5% | 安定志向の人が多く、社内教育体制や福利厚生が整っている企業が多い。キャリアアップの転職はあるものの、総じて離職率は低め。 |
| 公務員(複合サービス事業) | 7.8% | 身分の安定や福利厚生が整備されている分、離職率は非常に低い。ただし近年は激務の部署などで退職例が増えているとの声も。 |
離職率は業種や職種、雇用形態によって大きく異なります。特に非正規雇用者の離職率は高く、また、若年層や高齢者の離職率も高い傾向にあります。これらの要因を考慮することで、より詳細な分析が可能となります。
離職率の改善には、労働条件の見直しやキャリアパスの明確化、福利厚生の充実などが効果的です。業界特性に応じた施策を講じることで、定着率の向上が期待できます。
出典:
・厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」政府統計の総合窓口+12ホーム|厚生労働省+12パソナ+12
・e-Stat「雇用動向調査 年次別推移」AME&Company株式会社+3政府統計の総合窓口+3政府統計の総合窓口+3
業種別の平均値を把握する意義
- 自社の離職率を客観視できる
同じ業界の平均値と比べて自社の数値が高ければ、何らかの構造的な問題がある可能性があります。逆に低ければ、採用や教育の体制がしっかりしているといった強みが考えられます。 - 業界特有の課題を把握できる
たとえば人手不足が深刻な業界では、社員一人にかかる業務負担が大きくなりがちです。労働時間やシフト管理などに配慮し、現場の声を吸い上げる仕組みを強化する必要があります。 - 他業種からの学びを得られる
離職率の低い業種では、独自の教育体制や福利厚生、職場環境の整備が進んでいるケースが多いです。他業界の取り組みを参考に改善策を検討するのも有効な手段です。
離職率の高い業種の特徴
離職率が高い業種には、以下のような特徴が見られます。
- 労働時間・勤務形態の過酷さ
シフト制や夜勤が多い業種では、生活リズムが不規則になりやすく、精神的・肉体的な負担が増加する。 - 職場環境や人間関係の不備
忙しい現場ほどコミュニケーションが不足しがちで、トラブルが起きても解決しにくい。指導体制が整っていないと、社員が孤立を感じることも。 - 報酬・待遇面のミスマッチ
労働条件が厳しいにもかかわらず賃金が低い場合、より条件の良い企業や業種への転職を選択しやすい。
離職率の低い業種の特徴
一方で、離職率が低い業種には以下のような共通点があります。
- 安定した業務形態・福利厚生
規則正しい勤務体系や充実した研修制度が整っており、社員が長く働くメリットを感じやすい。 - 明確なキャリアパス
キャリアアップの仕組みや昇進ルートが見えやすく、社員が自分の将来像を描きやすい。 - 徹底したモチベーション管理
評価制度や面談制度などで個々の努力を適切に評価し、やりがいを感じられる環境を作っている。
離職率の低い企業は「働きやすさ」だけでなく、「成長できる環境」という要素も重要視しているケースが多いようです。
離職率の平均値と企業規模別比較
離職率は業種だけでなく、企業の規模によっても大きく異なります。ここでは、企業規模別の離職率平均値を表で示し、大企業と中小企業での違いや考えられる要因を解説します。
企業規模別 離職率平均値(令和5年)
| 企業規模(従業員数) | 離職率(%) | コメント |
| 5~29人 | 15.6% | 経営基盤が脆弱な場合が多く、待遇面やキャリアパスが限定的。人間関係や資金繰りなどの影響を受けやすい。 |
| 30~99人 | 16.0% | 中小企業だが、ある程度組織体制が整っている。部署の連携不足などがあると、離職要因になりやすい。 |
| 100~299人 | 19.0% | 中堅企業にあたり、独自の福利厚生・教育制度を持つところも。事業拡大期には離職率が上がる場合もある。 |
| 300~999人 | 16.1% | 一定のスケールメリットがあり、社員が安心して働ける環境が整備されやすい。昇進制度が明確かどうかがポイント。 |
| 1000人以上 | 14.2% | 大企業や上場企業が多く、給与水準や福利厚生が手厚い。一方、組織が大きい分、裁量範囲を感じにくい社員の離職も散見される。 |
出典:
- 厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」政府統計の総合窓口+12ホーム|厚生労働省+12パソナ+12
- リクルートワークス研究所「大企業若手従業員の離職率は上昇している」リクルートワークス研究所
企業規模別の平均値を確認する意義
- 自社の離職率を企業規模の平均と比較できる
同規模の企業がどの程度の離職率なのかを把握することで、自社の現状が「普通」なのか「高い(または低い)」のか判断しやすくなります。 - 課題の優先度を見極めやすい
資金力や人事制度の整い具合は、企業規模が大きいほど安定している傾向があります。自社の規模に応じて優先すべき課題(給与制度・研修体制など)を整理することが重要です。 - 将来の組織拡大に備えられる
企業が成長し、従業員数が増えるにつれて求められる制度やマネジメント手法は変わります。離職率の動向を参考にしながら、先回りして労働環境を整備しておくと、人材確保と定着がスムーズです。
大企業と中小企業の離職率の比較
一般的に、大企業のほうが中小企業よりも離職率が低い傾向があります。背景としては、次のような要素が考えられます。
- 待遇面の差
賃金水準や福利厚生が充実しているため、大企業では社員が長く働きやすい。 - 教育制度の充実
研修プログラムやOJT体制が整っているため、新人・若手社員の離職が抑制される。 - ブランド力・安定性
社会的信用度が高く、将来への不安が少ない。外的要因による倒産リスクが相対的に低い。
出典:
・2023年厚生労働省 性、企業規模別入職・離職率
離職率と企業規模の関係性
企業規模が大きいほど、資本力やノウハウが蓄積されており、雇用や職場環境が安定しやすいと考えられます。ただし、大企業でも社風や業種、部署ごとの仕事の特性により離職率が上下することも少なくありません。一方、中小企業でも魅力的な理念や柔軟な経営姿勢を打ち出すことで、社員がやりがいを感じ離職率が低下するケースもあります。
要するに、単純に「大きい企業だから離職率が低い」とは限らず、経営戦略や組織風土、社員教育の仕組みなど、多角的な要素が影響を与えているのです。
離職率の高い企業の課題
離職率が高い企業は、採用や企業イメージ、労働環境など、様々な面で課題を抱えがちです。ここでは代表的な3つの課題を取り上げます。
採用コストの増加
高い離職率の企業は、常に新しい人材を補充する必要に迫られます。求人広告費やエージェント手数料、面接・選考の工数が嵩むだけでなく、新人教育にかかる時間と費用もかかり、結果として採用コスト全体が増大。企業の経営を圧迫する要因となります。
企業イメージ悪化
社員の離職が続くと、外部から見た企業の評判にも影響します。求人情報サイトなどの口コミで「すぐ辞める人が多い」という印象が広まると、優秀な人材から敬遠されかねません。また、既存社員のモチベーションが低下し、悪循環に陥るリスクも高まります。
労働環境の悪化
頻繁な人材の入れ替わりにより、社内のコミュニケーションが不安定になりやすいです。ノウハウの継承が不十分なまま退職者が出れば、現場の負担が増加し、残った社員のモチベーションや健康状態に悪影響が及ぶ可能性があります。長時間労働やパワハラ体質などが見過ごされやすくなる点も大きな問題です。
離職率を改善するには?
離職率を改善するためには、経営陣と現場が一体となって環境整備や意識改革を進めることが大切です。以下にいくつかのアプローチを示します。
- 待遇面の見直し
賃金水準や昇進ルート、福利厚生などを定期的に評価し、業界水準とのギャップを把握する。必要に応じてベースアップや賞与制度、通勤手当の拡充などを検討する。 - 柔軟な働き方の導入
リモートワークやフレックスタイム制など、社員が生活と仕事を両立しやすい制度を導入。ワークライフバランスを重視する傾向の強い若手人材の満足度向上につながる。 - 教育・研修の充実
入社時の研修だけでなく、定期的なスキルアップ研修や資格支援制度を設ける。キャリア形成を支援する取り組みを明確に打ち出すことで、「成長できる職場」としての魅力を高める。 - 評価制度・コミュニケーションの最適化
目標設定と評価のプロセスが不透明だと、社員がやりがいを失いやすい。定期的な面談や360度評価の導入などを行い、社員同士のフィードバック文化を醸成する。 - 組織風土の改革
待遇や業務内容以外にも組織風土が問題となっている。コミュニケーションを活性化させる、従業員の声を反映させる、経営層が積極的な改革の姿勢を示すことが重要。
これらの取り組みを複合的に行うことで、社員が「この会社で働き続けたい」と思う環境を作り出し、離職率を抑えることができます。
まとめ
離職率は企業の健康状態を示す重要な指標です。業種や企業規模、経済状況などによって平均値は変動するため、自社と同業界・同規模の水準を把握し、適切な対策を講じることが不可欠となります。離職率が高まると採用コストや企業イメージが悪化し、組織力の低下につながりかねません。
なお、Tayoriを活用すれば、社内外からの問い合わせや意見を集約し、社員とのコミュニケーションをスムーズにする仕組みを構築できます。 働きやすい環境を整える一助として、ぜひ導入を検討してみてください。